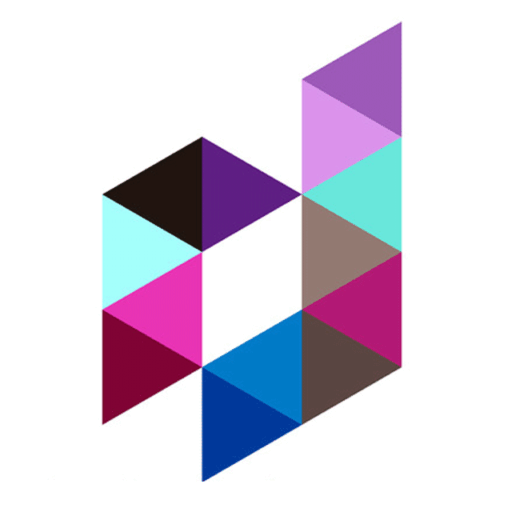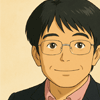はじめに
資産運用の選択肢として、「土地を購入して資産価値の上昇を狙う」という方法は古くから存在します。しかし、現在の日本においても「土地が今後値上がりする」と断言できるかどうかは、立地・用途・時期・税務面を含めた多角的な判断が必要です。
本稿では、税理士という視点から、土地購入を資産運用と位置づけた場合に「今後値上がりが期待できるか」「どういう条件なら値上がりが望めるか」「税務面・リスク面で注意すべき点は何か」を整理します。
土地価格の過去の推移と今後の見通し
地価公示・都道府県地価調査による現状
国土交通省が実施する「地価公示」によれば、令和7年(2025年)1月1日時点で全国の標準地価格が、住宅地・商業地ともに 4年連続で上昇 し、上昇幅も拡大しています。国土交通省+2国土交通省+2
また、「都道府県地価調査」(7月1日時点)は、各都道府県内の基準地における価格を把握しており、地域によって上昇・横ばい・下落の動きに差があります。国土交通省+1
今後の見通し
このような過去データから「土地価格は今後上がる可能性がある」と一定の期待が持てますが、注意すべき点も多くあります。例えば、都市部・人気エリアの再開発・インフラ整備などプラス要因がある地域では上昇幅が大きくなりやすい一方、人口減・地方圏の過疎化・供給過多な地域ではむしろ価格が横ばい・下落となる可能性があります。
さらに、インフレ・金利動向・税制度・土地利用規制の変化も価格に影響を与えます。税理士としては、こうしたマクロ要因と地域要因を組み合わせて判断すべきです。
土地購入のメリットとリスク
メリット
- 現物資産としての安定性:土地は株式・債券のような流動性資産とは異なり、「形ある資産」として保有できます。インフレ時には「実物資産」に価値が移りやすいという見方もあります。
- 相続税・贈与税対策の観点:土地を適切に評価・保有することで、節税・相続対策としても活用できます。税理士の視点からは、この点を戦略的に考える余地があります。
- 長期保有によるキャピタルゲインの可能性:立地が良く、需要の高い土地を早期に取得しておけば、将来的に売却益が得られる可能性があります。
リスク
- 地価下落リスク:地域の人口流出・産業構造の変化・土地の用途転換不可などから、価格が下がるリスクがあります。
- 維持コスト・税負担:土地を保有するだけでも固定資産税・都市計画税・管理維持費用などがかかります。特に収益を生まない土地ではコストだけが残る恐れがあります。
- 流動性の低さ:土地を売却するには時間やコストがかかる場合があります。急ぎで資金化するには難しいケースがあります。
土地の値上がりが期待できる条件とは?
土地価格の上昇を期待できる条件を整理すると、以下のようなものがあります。
- 地域の発展性・交通・インフラ:駅近・再開発・物流拠点・観光・IR整備など、今後発展が見込まれる地域であることが要件です。
- 需要と供給のバランス:土地利用が限定され、供給が一定以下である地域では価格が上がりやすく、反対に供給過多・需要低迷地域では下げ傾向が強くなります。
- 用途・法制度の変化:用途地域の見直し、容積率の見直し、用途転換可能性等があると、土地の価値が増す可能性があります。また税制改革(例えば、相続税対策用土地評価の見直しなど)も影響を及ぼします。
- マクロ経済・金融環境:金利が低い状態やインフレが進むと実物資産に目が向けられ、土地の価値にも上昇圧力が掛かる可能性があります。
税理士の視点から見る土地投資のポイント
税理士として特に注意すべき観点を以下に列挙します。
- 購入前の収支シミュレーション:土地購入価格、固定資産税・都市計画税、維持コスト(管理費・除草・土壌改良等)、売却時想定価格・期間を含めたキャッシュフローを整理すべきです。
- 法人購入 vs 個人購入の比較:法人名義での土地保有、個人名義での保有、それぞれのメリット・デメリット(税率・減価償却・法人税・相続税)を整理して判断します。
- 税務調査・評価のリスク:土地の評価・簿価・価格動向が市場と乖離していると、税務調査時に「過大評価」や「未申告資産」として指摘される可能性があります。取得時点から適正な価格・用途を記録しておくことが重要です。
- 出口戦略の明確化:土地は買ったら終わりではなく、数年後の売却も視野に入れた戦略が必要です。実際に売却できるか、買手が付くか、用途転換できるかを見据えておくべきです。
まとめ:今、土地を買うべきか?
結論として、「土地を購入して値上がりを狙う」という戦略は、以下の条件下で有効と考えられます。
- 立地・用途・将来性が明確に優れている土地であること。
- 維持コスト・税負担・流動性等のリスクを理解・許容できること。
- 税務・法務・収支計算を専門家(税理士・不動産鑑定士)とともに慎重に行っていること。
一方で、「漠然と土地=値上がりする」という思い込みだけで購入を進めるのは危険です。資産の一部を“不動産(=土地)”に分散投資するという視点で検討し、他資産(株式・債券・投資信託等)とのバランスも意識すべきです。