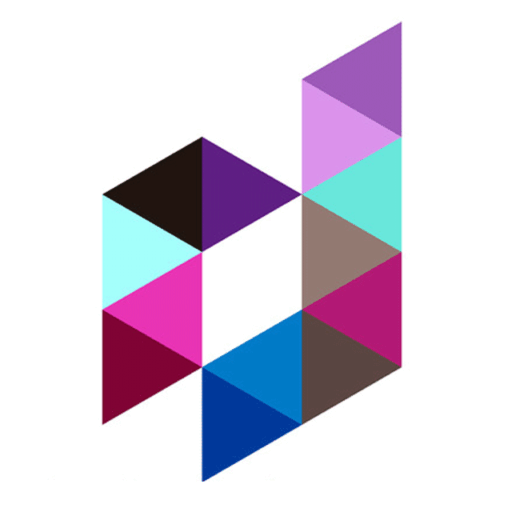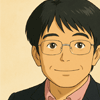日本のインフレーションは一時的か、長期的か?税理士の視点から見た今後の展望
ここ数年、日本では物価上昇が続いています。これまで長い間「デフレ経済」が当たり前だった日本にとって、今のインフレ傾向は大きな変化です。
では、このインフレーションは一時的なものでしょうか。それとも、長期的に続くのでしょうか。税理士として経済の動きを見ている立場から、整理してみたいと思います。
1.今の日本のインフレの現状
日本銀行の発表によると、2025年現在の消費者物価指数(CPI)は、すでに2%を上回る状態が続いています。これは日銀が目標とする「物価上昇率2%」を超えており、物価上昇が定着しつつあるとも言えます。
背景には、エネルギーや食品などの価格上昇、円安による輸入コストの上昇、人手不足による賃金上昇など、複数の要因が絡み合っています。
2.インフレが「一時的」と考えられる要因
まず、一時的なインフレである可能性についてです。
物価上昇の大きな要因のひとつは、原材料やエネルギーの輸入コスト上昇です。これは世界的な要因によるものが多く、日本だけの問題ではありません。
また、ウクライナ情勢や中東の不安定さなど、地政学的なリスクも一時的に物価を押し上げています。こうした要因が落ち着けば、インフレ率も徐々に落ち着く可能性があります。
つまり、外部要因による「コストプッシュ型インフレ」は、一時的で終わる可能性が高いといえます。
3.インフレが「長期化」する可能性
一方で、インフレが長期化する可能性も指摘されています。
特に注目すべきは、「賃金上昇」と「価格転嫁」の流れです。人手不足を背景に、多くの企業が賃上げを行っています。これが継続すれば、企業はコスト上昇を価格に反映せざるを得なくなり、「賃金→物価→賃金」という好循環が生まれます。
また、これまで価格転嫁に慎重だった企業も、最近では値上げを受け入れる社会的空気が広がっています。これは、長期的にインフレが定着していく兆しとも考えられます。
つまり、今の日本は「デフレ体質からインフレ体質へ」と、経済の構造が少しずつ変わり始めている可能性があるのです。
4.税理士の視点から見た実務への影響
インフレが続くかどうかは、経営や税務の実務にも大きく関わります。
まず、仕入れコストや人件費が上昇すれば、利益率の低下を招くおそれがあります。そのため、価格設定の見直しや、原価管理の強化が求められます。
また、賃金上昇が進むと、人件費負担は増えますが、人材確保には必要な対応でもあります。助成金制度の活用や、賃上げに伴う節税策の検討も重要です。
さらに、インフレ局面では、現金の価値が目減りする一方で、借入金の実質負担は軽くなります。資金繰りや投資計画を考える際にも、物価上昇を前提としたシミュレーションが欠かせません。
5.今後の見通しとまとめ
日本のインフレーションは、現時点では「一時的な要因」と「構造的な要因」が混在している状況です。
短期的にはエネルギー価格や為替の影響で上下する可能性がありますが、長期的には賃金上昇や企業の価格転嫁が進み、緩やかな物価上昇が定着していく可能性が高いと考えられます。
税理士としては、経営者や個人事業主の皆様に、「物価上昇を前提にした経営判断」を意識していただきたいと感じています。
価格改定のタイミング、賃金の見直し、資金繰りの調整など、早めの対応が今後の安定経営につながります。
今後も政府や日銀の政策動向、世界経済の変化を注視しながら、インフレ時代の経営を一緒に考えていく必要があります。
(執筆:舩橋信治税理士事務所 税理士 舩橋信治)
投稿日:2025年10月21日